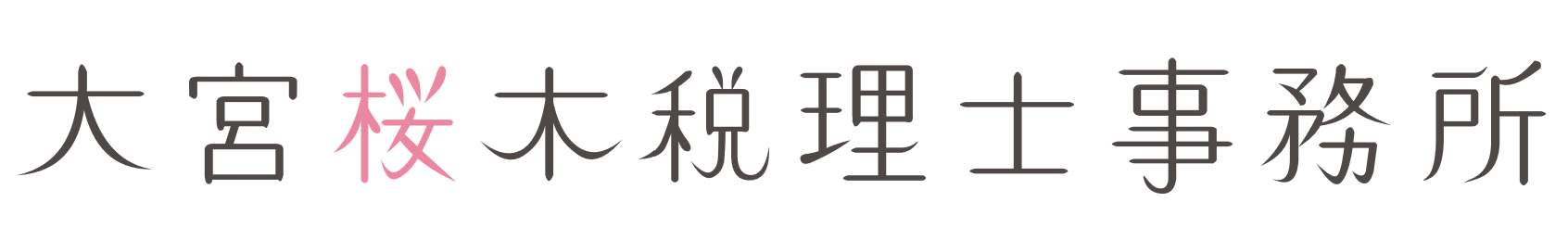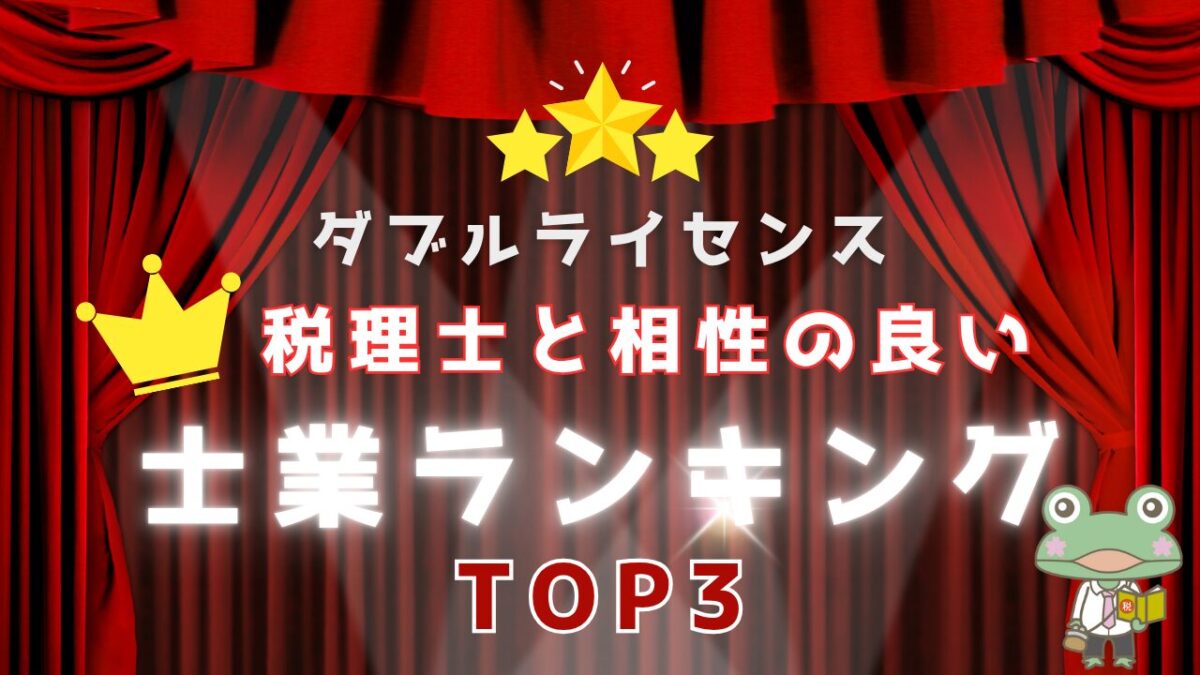この記事でわかること

- 税理士と相性の良い資格
- 税理士から見た社労士の実務
- 税理士×診断士の実務
- 税理士から見た行政書士の実務
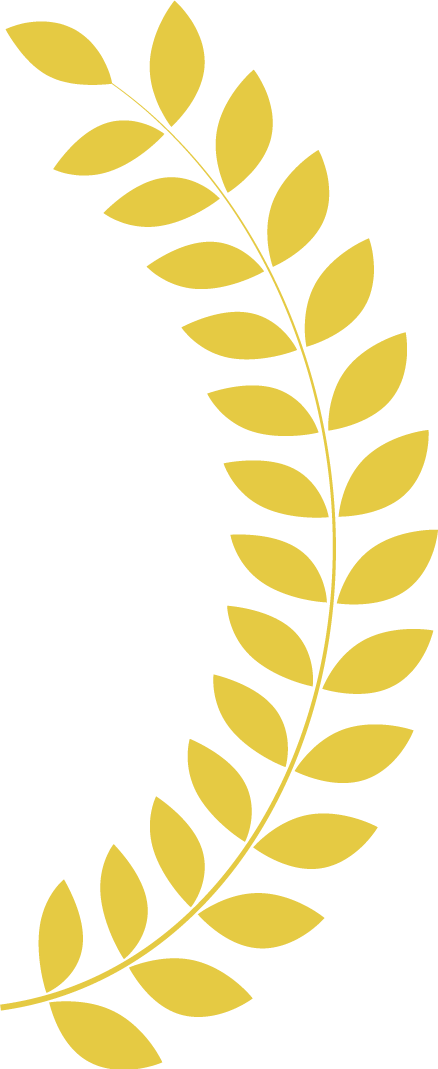
ダブルライセンスにあこがれて

よく「ダブルライセンス」という言葉を耳にします。ダブルライセンスなら独立してもうまくいきそうだなぁって。
税理士と相性の資格ってあるのでしょうか?

税理士はその資格単体でも十分に食っていける資格ですが、ダブルライセンスになることによって、安全度がさらに増します。ちなみに私は中小企業診断士と税理士のダブルライセンスですよ。中小企業診断士のほかに相性がいいものがいくつかありますよ!

税理士と相性の良い資格を教えてください!!

承知しました!今回は税理士と相性の資格ランキングということでお話していきますね!
前提
このランキングは私が実務を通じて実際に感じた、実務シナジーがありそうだと思うものをランキング化したものです。
税理士は大きく「資産税特化」と「法人税特化」に分けることができますが、私の場合は法人税特化の税理士になります。(資産税の申告もしていますが)
資産税特化の税理士の場合はまた変わってくるのでその点ご留意ください。
異論は、、、、認めます(笑)
第1位:社会保険労務士(社労士)
なぜ相性が良い?
- 給与計算で月額報酬アップ!!
- 定期的な手続きで臨時報酬獲得!!
給与計算のニーズはかなり多いです!
役員報酬などは定期同額給与のため一度報酬を決めてしまえば、報酬の内容が大きく変わることはないため、従業員が役員のみの小さな会社の場合は給与計算の報酬は頂いてないです。
しかし、従業員を雇用して事業を行うケースは決して少なくないです。従業員の場合は、残業などの関係から報酬が毎月変動するので、計算が難しく、社労士を入れるか、給与計算ソフトを入れてもらうようにお願いしています。
その場合に、社労士を入れるケースも少なくなく、私がそのままできれば月の顧問料を底上げできるのになぁ~と感じています。ちなみに、給与計算を顧問料の範囲内でと言われることもあります。役員のみの場合は請け負いますが、従業員がいる場合は無理ですと即答してます(笑)
定期的な手続きもかなり多いです。
法人を設立した場合は社会保険や労働保険の加入手続きなどありますし、労働保険の年度更新、算定基礎届などは毎年発生する手続きです。
手続き自体はそこまで難しいものではないのですが、社労士の独占業務のため税理士資格のみだと手続きすることはできないです。
具体的に何が増える?
- ストック(毎月):給与計算
- スポット(季節・臨時):
- 4〜6月:労働保険年度更新
- 6〜7月:算定基礎届(標準報酬の見直し)
- 随時:月額変更届(随時改定)、賞与支払届、社会保険・労働保険加入手続
※ 社会保険の手続等は社労士の独占業務。必ず有資格者が担当。

税理士取った後に何を勉強するかと聞かれたら社労士と答えます!昔に戻れるなら社労士を勉強したいです。
第2位:中小企業診断士
なぜ相性が良い?
- 事業計画作成で融資・補助金申請のサポートで臨時収入
- 公的機関からの受注機会増加で売上増加
実際に私が税理士×診断士として活動してますが診断士としての売上もそれなりに上がってきています。
診断士は何といっても決算書などの分析の深度が増す点が税理士とシナジーが高いです。お客様へ数字の報告は必須ですので診断士のスキルは付加価値向上、信用力向上につながります。
実際の受注機会とすると、補助金申請や融資サポートなどが挙げられます。具体的には事業計画の作成サポートですね。外国人実習生を雇い入れる際の財務評価書なども作ることがありますよ。スポット契約ではありますが、そこから顧問契約に発展というケースも少なくないです。
中小企業診断士になると、公的機関との受注機会が増加します。診断士は公的機関とのつながりがあることが多く、窓口相談、専門家派遣、研修・講師、補助金事務局など受注機会が増えます。その中で税理士を持っていると、税務相談など税務の知識を武器とした、ほかの診断士との差別化が図れるので「診断士を持っていて、税理士でもある方に」というケースも少なくないです。
あとは診断士の会費が安いのもダブルライセンスと相性が良いです。
資格の維持費用は年間5万円前後。登録初年度は入会金3万円も追加でかかりますが税理士や社労士などほかの資格と比べてもかなり安いです。
実務シナジーが大きい
税理士×診断士で、決算書の分析→打ち手への落とし込みまで一気通貫
数字の説明が深まり、提案の説得力増加
具体的な受注導線が明確
- 補助金申請・融資サポート:事業計画の作成支援で着手しやすい入口。
- 財務評価書の作成:例)外国人実習生受入時の財務評価書などのスポット需要。
- スポット→顧問化:税務顧問契約に発展
公的機関経由のチャンスが増える
窓口相談/専門家派遣/研修/補助金事務局などの公的案件へのアクセスが拡大
“税理士×診断士”だから選ばれる
税務の知見を武器に、**「診断士+税理士にお願いしたい」**という指名が発生。他の診断士との差別化につながる

診断士も税理士との相性は抜群です!ただ診断士は独占業務がないんですよね。。。独占業務があればもっと人気の出る資格なんですけどね。
第3位:行政書士
なぜ相性が良い?
- 許認可系の仕事の受注で売上アップ!
- 税理士からなら試験を受けずに登録可能
建設業許可、介護タクシーのような一般乗用旅客自動車運送事業、人材派遣業許可など許認可関係の依頼は少なくないです。スポットのお客さんから税務顧問という流れも可能ですし、既存顧客の事業拡大で許認可が必要となるケースも少なくないです。
私の場合は、建設業のお客が多いので、建設業許可の新規申請はもちろん、建設業許可の承継などのケースもあります。税理士単体だとこの辺の業務ができないので、ダブルライセンスなら一気通貫でこの辺も対応することが可能になります。
税理士と行政書士のダブルライセンスは数は多い方だと思います。これは税理士を取得すると行政書士試験が免除になるからですね。無試験で登録できてしまうということです。行政手続きには決算書などが必要なケースも多く、税理士ならその辺も簡単に準備できてしまう点は親和性が高いと感じます。
上記2つの資格に比べると、行政書士はスポットの依頼になりがちなので第3位という結果になりました。
許認可は“顧問化の入り口”にも“既存先の拡張”にも効く
建設業許可・介護タクシー(福祉輸送限定のタクシー許可)・労働者派遣業などは、スポット受注から税務顧問化につながりやすく、既存顧客の事業拡大に伴う追加受注も狙える。
税理士×行政書士の“相性が良い”理由
税理士資格があれば行政書士は試験免除で登録可(欠格事由等の確認・各会の手続は必要)。許認可申請は決算書・財務資料の提出が絡むことが多く、税理士の強みがそのまま申請品質・スピードに直結。
行政書士の独占業務(官公署提出書類・権利義務・事実証明書類の作成等)は有資格者が担当。記名押印や名義貸しは不可。

中小企業診断士の試験に合格できなかったら行政書士でダブルライセンスしようと思っていました。
まとめ

税理士のダブルライセンスについて書かせていただきましたが、あくまでも私の実務上の経験が元になっている点ご了承ください。

ダブルライセンスじゃないと独立はうまくいかないですか?

そんなことないですよ。私は独立が怖くて少しでもリスクを減らすためにと、診断士の資格を取りましたが、税理士だけでも十分やっていけたかなと思ってます。

ただ、診断士の資格を取得したことは事業をやるうえでプラスになっているし、今のところは事業も順調に成長している。診断士の売上も一定あるし、ダブルライセンスはあるに越したことはないですよ!!